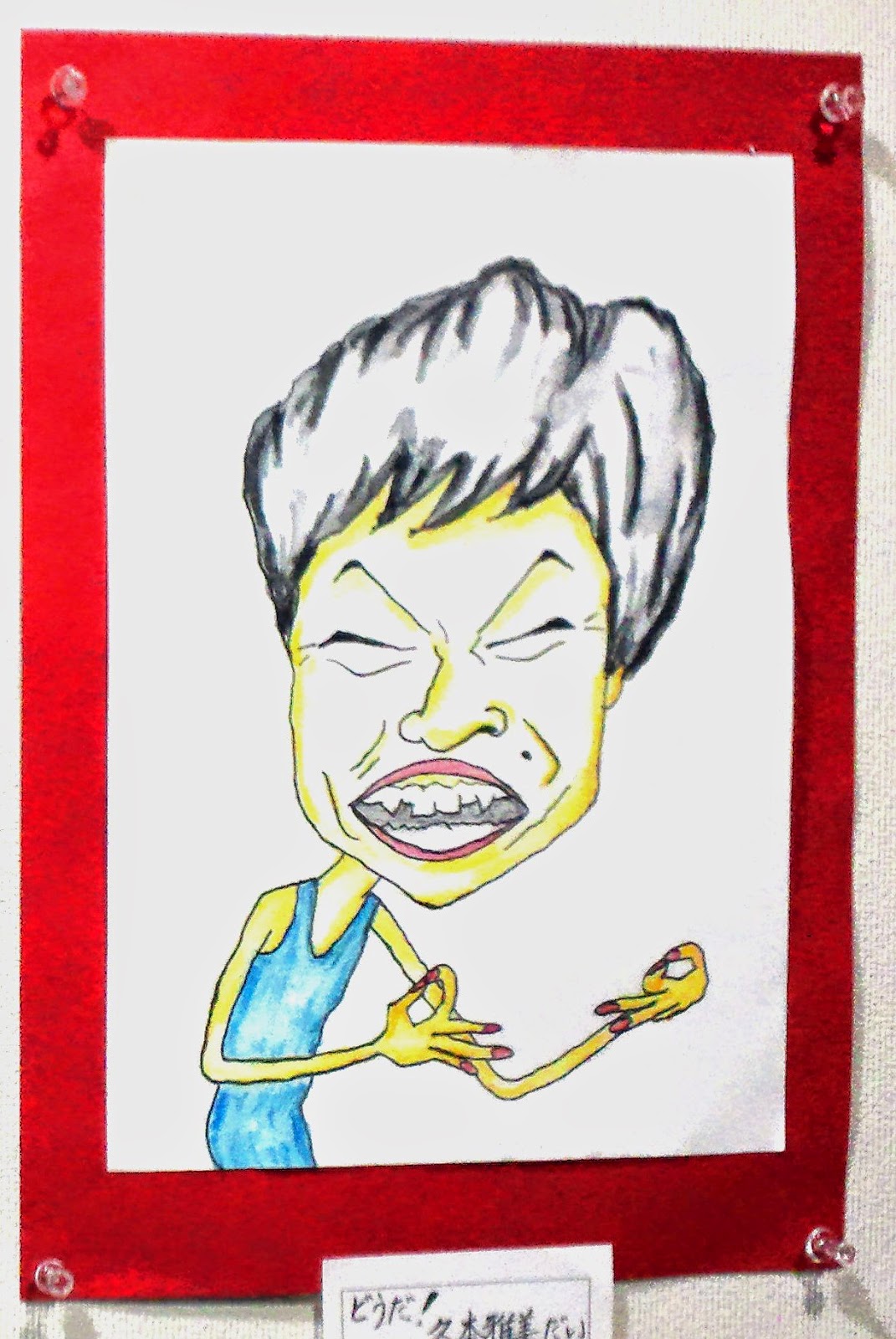今年の夏は天候不順で我が家の狭い庭とプランターにも、例年とは違ういろんな異変が起きているようだ。それに加えて、7月下旬から9月初めまでスペイン語短期留学の為家を留守にしていて、留守宅では水やりは欠かさずしてくれてはいたが、トマトやナスやキューリの脇芽の管理などまで手が回っていなかった。もっともそこまでするのは留守宅部隊(妻と娘)では無理で、頼んではいなかった。
9月2日に帰国してから早や1ヶ月近く、ちょっとづつ立て直していき、ちょっと一息ついた。
丸いミニトマト: 3週間ほどかかって赤くなった。皮は少し硬いが味は上々。
楕円のミニトマト: 枝を整理したら再び実がたくさん付きはじめた。花もたくさん咲いている。
ピーマン、シシトウ、ナス: トマトと同じナス科で、枝を整理したら実が付きはじめた。
芽キャベツ: 今年始めの冬に収穫した木(野菜も「木」といったかな?)が夏越しして再び芽キャベツが取れそうな様相だ。
エンダイブ: おいしく食べるためにはひと手間かけないといけないが、それをしていないので食べても苦いし固い。
三つ葉: 放っておいても種がこぼれてどんどん増える。 薬味だけでなくお浸しなんかも出来る。
アサツキ: 植え替えなかったし、土も良くなかったので、ひょろひょろ。
ジャガイモ: どういうわけか今頃芽が伸び出した。こんなのでジャガイモが採れるのか。ちょっとネットを見たら、「秋ジャガ」と言うのがあるそうなので、楽しみにしておこう。
オクラ: 順調に実を付け続けている。
サツマイモ: 鳴門金時、男爵、安納イモの3種。生育は順調。収穫は10月~11月だから、もう少し。
トウモロコシ: 良い土に植えたのは良く育っておいしいのが2本(たったの2本ですが)採れた。こちらは土が悪かったせいか生育が悪くてひょろひょろ。ミニコーンくらいは楽しめるのかなあ。
ネギ: 細ネギや太ネギが育っている。
ラズベリー: 枝を整理していなかったので実付きが悪い。
クワイ: 近所の方に昨年頂いた残りを植えてみた。年末には収穫できるかも。
温州ミカン: 15個ほどなっている。
ミョウガ: 毎年7月~8月に採れて、秋に採れる事はなかったように思うが、今年は今頃になってまた土から芽が見え始めた。
ヒャクメカキ(百目柿): 2個収穫できそう。ちょっと大きめで、期待大。テニスボールくらいの大きさがある。