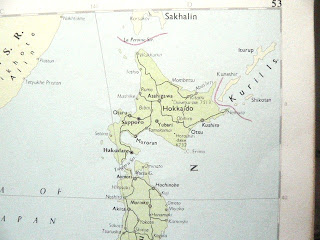トランペットの個人レッスンを月に2回、毎回1時間お願いしている。今日はその日だった。
先生に前回のレッスンで、「ピッコロトランペッットは人によってはハイノート(高音)の練習に良いケースがある」と聞いて、さっそく中国製の「マイケル」ブランドのピッコロトランペットを手に入れたのがほぼ2週間前。
このピッコロトランペット、外観が「ストンビ(STOMVI)」トランペットにそっくりだという事は前回書いた。
肝心の「音」については初心者(先生はお世辞で、中級者と上級者の中間ぐらいだと言って下さるけど―― 初級者・中級者・上級者については、後日再度考えて書いてみる事にする)の僕にはわからない。はたして「プロ」の技術で吹き、「プロ」の耳で聞いたらどうなのか?
1.音が「まろやか」
僕の感想では「薄っぺらい」というのが印象だったが、基本的にはピッコロトランペットというのは、管の長さが短いし小さいから普通のトランペットとは違います、という事であった。先生愛用の先生用特別仕様の「ヤマハ」ピッコロトランペットの音を聞かせて頂いたが、明らかに音が「豊か」というか「ふくよか」という感じで、「マイケル」とは全く違う気がした。
2.高音が出にくい
どこまでの高音なのか。たぶん僕がいま出せる音よりはるか高い音の事だろうと思う。
3.音程
ひどい音程だ、とは指摘されなかったので「まあまあ」なのか。
外観について先生からもう2つ、「ストンビ」と似ている点を教えて頂いた。
1.管の接続部の樽のような形
 |
| 左が「ストンビ」、右が「マイケル」 |
 |
左が「ストンビ」トランペット用
右が「マイケル」ピッコロトランペット用
同じ大きさのマウスピースを比べると「そっくりさ」がもっとわかる。
|
溶接の仕上げがもう一つ、とか、よく見るとピストン部が少し曲がっているような・・・・・とか言うのはあるが、どこのメーカーでも同じだけどみんな一つ一つ手仕上げだからね、との事。練習には十分使えるレベルだ。